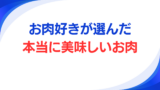「オージービーフってなんかまずい…」「臭いし、硬くて国産牛のほうがいい」と感じたことがある人は少なくありません。
実はそれ、オージービーフそのものが悪いのではなく、特有の肉質と調理法のズレが原因であることが多いんです。
オージービーフは日本の牛肉とはまったく性質が異なり、適切な下処理・焼き方・選び方をするだけで驚くほどおいしくなります。
本記事では、
- なぜ「まずい」と感じる人が多いのか
- 臭みや硬さの原因
- おいしく食べるための下処理・調理のコツ
- 国産牛との違いと選び方のポイント
をわかりやすく解説します。
「オージービーフが苦手」という印象をガラリと変えるヒントが、きっと見つかるはずです。
オージービーフが「まずい」と言われる理由
特有の臭い・風味の違い
オージービーフが「まずい」と言われる一番の理由は、独特の“風味”にあります。
国産牛と比べると、オージービーフは放牧による自然な飼育が多く、牧草を主なエサとしているため、肉に独特の草の香り(青臭さ)や野性味が残ることがあります。
これは品質の悪さではなく、肉の個性として現れるものです。しかし、日本人の多くが慣れ親しんでいるのは、サシ(脂)が多く、柔らかく甘みのある和牛。
そのため、この独特の香りを「臭い」と感じ、「まずい」と思ってしまう人が少なくありません。
また、この風味は加熱方法によって強く出ることもあり、ステーキの焼き方次第で好き嫌いが大きく分かれる特徴でもあります。
特に、強火で短時間焼いたときや、冷凍・解凍を繰り返した肉では臭みが強く出やすく、苦手意識につながりやすい傾向があります。
硬いと感じやすい肉質の特徴
オージービーフの肉質は国産牛に比べて引き締まっており、しっかりとした赤身が多く、脂肪分が少ないのが特徴です。
これにより、焼き加減を誤るとパサついたり、硬くなったりしやすいというデメリットが出ます。
一方で、しっかりとした歯ごたえを好む人にとっては「肉を食べている感」が強く、むしろ好まれることもあります。
ただし、和牛のような「とろける柔らかさ」を期待して食べると、ギャップが大きく「硬い=まずい」と感じてしまうケースが多いのです。
適切な下処理と調理を行えば柔らかく仕上げることは十分可能であり、「硬さ」は必ずしもデメリットではありません。
赤身中心で脂身が少ない構造
オージービーフの特徴として、赤身が多く脂身が少ないことが挙げられます。
脂が少ないと口の中でとろけるような食感はなく、淡白な印象になりやすいのです。
そのため、脂の旨みを好む日本人にとっては、物足りなさを感じやすく「まずい」と感じる要因となっています。
しかし、この赤身中心の肉はヘルシー志向の人や、筋肉増強・ダイエット目的で肉を食べる人には非常に人気があります。
味や香りの印象は調理法や合わせるソースでも大きく変わるため、赤身を活かしたレシピを選ぶことで「まずい」を「おいしい」に変えることが可能です。
調理方法が合わないケースが多い
オージービーフを「まずい」と感じる人の多くは、調理方法が和牛向きのままになっていることがあります。
和牛は脂が多いため、火を通しすぎても柔らかさや旨味を保ちやすいですが、オージービーフは火を通しすぎると一気に硬くなり、臭みも増します。
ミディアムレアで焼き上げるなど、火入れの技術が味を大きく左右するのです。
また、調理前に冷たいまま焼いてしまうと中心部に火が入りづらく、表面だけが固くなることもよくある失敗です。
オージービーフは「焼き方の工夫次第」で、まったく印象が変わる肉なのです。
国産牛との食感・風味の差
日本で「まずい」と言われがちな背景には、国産牛(特に和牛)との比較があります。
和牛は霜降りの脂が豊富で、とろけるような柔らかさと甘みが特徴的です。
対してオージービーフは赤身中心であっさりとした味わい。
その違いを知らずに「同じ牛肉」として食べると、「味が落ちる」「臭い」といった印象を持たれてしまいます。
しかし、これは「優劣」の問題ではなく、味の方向性の違いです。
適切な調理や味付けをすれば、国産牛とは違った魅力がしっかりと引き出せます。
「和牛の代わり」ではなく、「別物の肉」として理解することが、まずさを感じなくなる第一歩といえます。
「臭い・硬い」と感じるのはなぜ?
飼育環境と飼料の違い
オージービーフは、自然放牧で牧草を食べて育つ「グラスフェッド」が多く、日本の牛と比べて飼育環境やエサがまったく異なります。
この牧草由来の香りや風味が、臭みとして感じられる最大の原因です。
一方、和牛は穀物中心の飼料で育てられるため、香りが穏やかでクセが少ない傾向があります。
また、放牧環境では筋肉がしっかり発達するため、肉質も引き締まり、柔らかくするには調理の工夫が必要になります。
つまり、「臭い・硬い」と感じるのは、飼育環境による肉質の違いが根本的な原因といえます。
輸送・熟成過程による風味の変化
オーストラリアから日本へ輸入される過程で、オージービーフは数週間かけて輸送・熟成されます。
この過程で独特の熟成香が生まれ、日本人には馴染みのない匂いになることがあります。
特に冷凍・解凍を繰り返した肉では、香りが強くなりやすく「臭い」と感じる人が多いのです。
一方で、この熟成によって肉の旨味が増している部分もあります。
ただし、正しい調理をしないとその旨味が引き出せず、臭みばかりが目立ってしまうことがあります。
グラスフェッドとグレインフェッドの違い
オージービーフには大きく分けて「グラスフェッド(牧草飼育)」と「グレインフェッド(穀物飼育)」があります。
グラスフェッドは自然な風味が強く、赤身も引き締まっているため、調理次第で硬く感じることがあります。
一方、グレインフェッドは脂のノリがよく、和牛に近い味わいを持っているため、日本人の口に合いやすい傾向があります。
「オージービーフ=まずい」と感じた人の多くが、グラスフェッドタイプをそのまま焼いて食べているケースが多いです。
実は、選ぶ種類によって味の印象がまったく変わることは、あまり知られていません。
冷凍・解凍の仕方で味が大きく変わる
オージービーフは冷凍保存されることが多く、解凍の仕方次第で食感や臭いに大きな差が出ます。
急激に解凍するとドリップ(旨味成分)が大量に出てしまい、臭みやパサつきの原因になります。
冷蔵庫でゆっくりと解凍し、常温に戻してから調理することで、風味と食感が大きく改善されます。
この解凍工程を適当にしてしまうと、「硬い」「臭い」「水っぽい」といった不満につながりやすくなるため、味を左右する非常に重要なポイントです。
日本人の嗜好とのギャップ
最終的に「まずい」と感じる背景には、日本人の肉に対する嗜好も大きく関係しています。
多くの日本人は、霜降り和牛の脂の甘みや柔らかさに慣れており、赤身主体で野性味のあるオージービーフとは方向性が異なります。
つまり、味覚の基準が違うため、おいしさの基準にギャップが生まれてしまうのです。
ただし、この嗜好の違いは慣れと調理法で克服できます。
実際、オージービーフは欧米では高評価を受けており、日本でも赤身志向の高まりとともに人気が上昇しています。
「まずい」という先入観を持たず、肉の個性を理解することが大切です。
オージービーフをおいしく食べる調理のコツ
下処理で臭みを抑える方法
オージービーフをおいしく食べるためには、まず「下処理」が非常に重要です。
臭みの主な原因は肉のドリップ(血液や水分)と外側の脂肪層に残る草の香りです。調理前にキッチンペーパーでしっかり水分を取り除くことで、焼いたときの臭いが大幅に軽減されます。
さらに、臭いが気になる場合は塩水や牛乳、赤ワインなどに軽く漬け込むのも効果的です。
特に牛乳に30分ほど浸すと、臭み成分が中和されやすく、やわらかさも増します。
また、すりおろしニンニクやハーブを活用したマリネも有効で、調理前の一手間で風味が驚くほど変わります。
常温に戻してから焼く重要性
冷たいままのオージービーフをそのまま焼いてしまうと、外側だけが焦げて中が生焼け、または加熱しすぎて硬くなる失敗が起こりやすくなります。
この失敗を防ぐには、調理の30分前には冷蔵庫から出し、常温に戻すことが大切です。
温度差をなくすことで、表面と中心部が均等に火が入り、臭みも出にくくなります。
また、常温に戻すことで焼き時間を短縮でき、肉汁を閉じ込めやすくなり、結果的に「ジューシーで柔らかい仕上がり」になります。
ステーキを柔らかく仕上げる焼き方
オージービーフの赤身肉をステーキにする場合、和牛と同じように強火で長時間焼くのはNGです。
ポイントは強火で表面を短時間焼き、あとは余熱で中まで火を通すこと。
これにより、硬くならずジューシーな状態を保ちやすくなります。
また、焼く直前に塩を振ると水分が抜けやすくなるため、味付けは焼き上がりの直前か焼いた後に行うのが理想です。
さらに、アルミホイルに包んで2〜3分休ませる「レスト」の工程を入れることで、肉汁が全体に行き渡り、しっとりとしたステーキに仕上がります。
煮込み・ロースト・スライスなど調理法の工夫
オージービーフはステーキだけでなく、煮込みやロースト、薄切りスライス調理に非常に向いています。
煮込み料理では肉の筋繊維がほぐれ、赤身でも驚くほど柔らかくなり、臭みもほとんど気にならなくなります。
ローストビーフではしっとりとした食感が活かされ、赤身の旨味がダイレクトに味わえます。
さらに、薄切りにして炒め物や焼きしゃぶにすることで、火の通りが均一になり、硬くなるリスクを最小限に抑えられます。
調理法を変えるだけで、「まずい」と言われがちな肉が「おいしい赤身肉」に生まれ変わるのです。
部位別のおすすめ調理方法
オージービーフは部位ごとに味わいや食感が大きく異なります。
例えば、リブアイやサーロインはステーキやローストビーフ向きで、やわらかくジューシーに仕上がります。
一方、モモやランプは脂が少ないため、薄切りで炒めたり、煮込みにするのがおすすめです。
また、肩ロースやブリスケット(バラ肉)はしっかりとした歯ごたえがあるので、長時間の煮込み料理にぴったりです。
部位に応じた調理法を選ぶことで、オージービーフの味わいを最大限に引き出すことができます。
国産牛とオージービーフの違いを知る
サシ(脂身)の有無と味わいの差
国産牛、特に和牛の最大の特徴は「サシ」と呼ばれる霜降り脂肪です。
このサシによって柔らかさや甘み、ジューシーさが引き立ち、日本人が「おいしい」と感じる味わいを作り出しています。
一方、オージービーフは赤身中心でサシが少なく、あっさりとした味わいとしっかりした歯ごたえが特徴です。
この差を知らずに食べると「物足りない」「まずい」と感じてしまう人が多いのですが、方向性が違うだけで品質が劣るわけではありません。
価格と品質のバランス
オージービーフは国産牛に比べると価格が安く、コスパが高いことが大きな魅力です。
国産和牛のようなサシは少ないものの、適切な調理を行えば十分に満足できるクオリティを持っています。
また、脂が少ない分ヘルシーで、たくさん食べても胃もたれしにくいのもメリットです。
「高い=おいしい」という先入観を捨てて、価格と味のバランスで見るとオージービーフは非常に優秀な食材といえます。
ヘルシー志向と赤身の需要
近年では「脂っこい肉より、赤身のヘルシーな肉を食べたい」という人が増えています。
オージービーフはこのニーズにぴったりで、たんぱく質が豊富で脂肪が少なく、ダイエット中やトレーニング中の人にも人気です。
栄養価の高さと価格の手頃さから、スーパーや外食産業でも多く利用されています。
日本では「和牛信仰」が根強いものの、海外ではむしろオージービーフのような赤身肉の方が主流であり、健康志向の高まりとともに評価が上がっています。
輸入肉の安全性と管理体制
オージービーフは厳しい輸出基準をクリアしており、品質管理・衛生面でも高いレベルを維持しています。
オーストラリアは家畜のトレーサビリティ(生産履歴の追跡)が徹底しており、どの牧場で育ち、どのように処理されたかを追跡可能です。
そのため、輸入肉=不安というイメージは過去のものであり、むしろ安全性の高さに信頼を寄せる消費者も増えています。
また、冷凍・チルド技術も進化しており、鮮度を保ったまま日本に届くため、品質が劣化することはほとんどありません。
どちらが優れているかは目的次第
結論として、国産牛とオージービーフのどちらが優れているかは一概には言えません。
霜降りの甘みと柔らかさを楽しみたいなら和牛、赤身の旨味とヘルシーさを重視するならオージービーフです。
また、価格面でも両者には大きな差があり、シーンによって使い分けるのが最も賢い選択といえます。
「和牛が上、オージービーフが下」という固定観念をなくし、それぞれの特性を理解して選ぶことで、よりおいしい肉の楽しみ方が広がるのです。
おいしいオージービーフを選ぶポイント
グラスフェッドとグレインフェッドの選び方
オージービーフには大きく分けて「グラスフェッド(牧草飼育)」と「グレインフェッド(穀物飼育)」の2種類があります。
グラスフェッドは自然放牧で育てられ、脂が少なく赤身が多いのが特徴。ヘルシー志向の人や赤身肉特有の風味を好む人に向いています。
一方、グレインフェッドは穀物飼料で育てられているため、脂のノリがよく、口当たりが柔らかく、日本人の好みに合いやすい味わいです。
「臭い・硬い」と感じた経験がある人は、まずグレインフェッドから試してみると印象が変わる可能性が高いです。
味の方向性を理解し、自分の好みに合った種類を選ぶことが、オージービーフをおいしく楽しむ第一歩です。
スーパーでの見分け方
スーパーでオージービーフを買うときは、ラベルと肉の見た目をしっかりチェックしましょう。
グラスフェッドかグレインフェッドかは、パッケージに明記されていることが多く、輸入元やブランド情報も確認できます。
また、肉の色味が明るすぎるものや、ドリップ(赤い液体)が多く出ているものは鮮度が落ちている可能性があります。
濃い赤色でハリがあり、ドリップが少ないものを選ぶのがポイントです。
真空パック・チルド商品のチェック
オージービーフは冷凍品とチルド品が販売されていますが、味にこだわるなら真空パックされたチルド商品がおすすめです。
真空パックは酸化を防ぎ、熟成によって旨味が増すため、冷凍肉よりも風味がやわらかく、臭みが出にくい特徴があります。
開封後はできるだけ早く調理するのがベスト。購入時に消費期限とパックの状態をしっかり確認しましょう。
脂の入り方・色で判断するコツ
見た目で選ぶときのポイントは「色」と「脂の入り方」です。
鮮やかな濃い赤色をしていて、うっすらと脂が入っているものは、程よいコクと柔らかさが期待できます。
一方、脂がまったくなく、筋が多い肉は調理に工夫が必要で、煮込みや薄切りに向いています。
また、脂の色が白っぽく透明感があるものは鮮度が高く、黄色がかっているものは時間が経過している可能性があるため注意しましょう。
評判の良いブランド牛も活用
オージービーフと一口に言っても、ブランドによって味や香りは大きく異なります。
たとえば、オーストラリア産でも高評価を得ている「グレートサザンビーフ」や「タジマ種系統」などは、臭みが少なく柔らかいと評判です。
価格も手ごろで、スーパーでも比較的手に入りやすいブランドが増えているため、初めて挑戦する人はこうしたブランド牛を選ぶと失敗しにくいです。
オージービーフを活用したおすすめレシピ
ステーキでおいしく食べるコツ
オージービーフの赤身は、ステーキでその旨味をダイレクトに楽しむのに最適です。
おいしく焼くコツは「強火で表面をカリッと焼き、余熱で中をじんわり仕上げる」こと。
火を通しすぎると一気に硬くなってしまうため、ミディアムレア程度で仕上げるのがベストです。
さらに、焼く前に常温に戻し、焼き上がり後にアルミホイルで数分休ませることで、肉汁が全体に行き渡り、しっとりとした食感になります。
煮込み料理でやわらかく仕上げる
「硬い」と感じやすいオージービーフも、煮込み料理にすれば驚くほど柔らかく仕上がります。
圧力鍋や長時間の弱火調理で筋肉繊維がほぐれ、臭みもほとんど感じなくなります。
赤ワイン煮やビーフシチュー、カレーなどの煮込み系は、特に相性の良いレシピです。
煮込み料理なら、肉質にこだわらず比較的安価な部位でもおいしく仕上げられるのも大きなメリットです。
薄切り調理で臭みを抑える
薄切りにして調理することで、臭みを感じにくく、加熱時間も短く済みます。
焼きしゃぶや牛丼、炒め物などに使うと、赤身の風味を活かしながらも柔らかく仕上げられます。
特に初心者には、この薄切り調理がもっとも失敗しにくい方法といえるでしょう。
焼くときは強火でサッと火を通すのがポイント。加熱しすぎると硬くなってしまうので注意が必要です。
香辛料・ソースで風味を引き立てる
オージービーフの独特の風味は、香辛料やソースを活用することで一気に印象が変わります。
ブラックペッパー、ガーリック、ローズマリーなどを使うと、臭みが抑えられ、香ばしさが増します。
ソースはステーキソースのほか、バター醤油や和風おろしソース、赤ワインソースなども相性抜群です。
香辛料やソースを活かすことで、「臭い・まずい」と感じる要素をポジティブな風味へと変えられます。
初心者でも失敗しにくい調理法
初心者におすすめなのは、「火を通しすぎない・薄く切る・香りを足す」という3つの基本を押さえること。
厚切りステーキをいきなり調理するよりも、薄切りでサッと炒める、煮込み料理にする、といった調理法が失敗しにくいです。
また、真空パックのチルド肉を使えば、臭みも少なく扱いやすいので、初めての人でもおいしく仕上げやすくなります。
まとめ:オージービーフは「まずい」ではなく「調理と選び方」次第
「まずい」と言われる理由の多くは調理法
オージービーフが「まずい」と言われる一番の理由は、肉そのものの品質ではなく、調理法や扱い方にあります。
和牛と同じ感覚で調理すると、臭みや硬さが目立ってしまい、評価が下がってしまうのです。
適切な焼き方・煮込み方を理解すれば、味の印象は大きく変わります。
選び方・下処理で味は大きく変わる
調理以前に「どんな肉を選ぶか」も非常に重要なポイントです。
グレインフェッドを選んだり、真空パックのチルド肉を使ったり、臭み対策の下処理をするだけで、味の差は歴然です。
「まずい肉」ではなく、「扱い方で差が出る肉」と考えるとイメージが変わるでしょう。
国産牛との違いを理解することがカギ
オージービーフと国産牛は味の方向性がまったく違います。
サシの甘みを楽しむ和牛と、赤身の旨味を活かすオージービーフを比較するのはナンセンス。
それぞれの特性を理解したうえで調理すれば、赤身ならではの魅力がしっかりと引き出せます。
コスパよくおいしく食べるコツ
オージービーフは手ごろな価格で買えるうえに、調理次第で高級肉にも負けない味わいが楽しめます。
焼き方・煮込み・香辛料の活用など、ちょっとしたコツを押さえるだけで満足度が一気に上がります。
コスパと味の両立を求めるなら、まさにぴったりの選択肢といえるでしょう。
苦手な人でもおいしく食べられる可能性
「オージービーフはまずい」と思っていた人でも、選び方と調理法を少し変えるだけで印象が一変します。
赤身肉ならではのうまみや食べごたえは、慣れてくるとクセになる人も多いもの。
苦手意識を持つ人こそ、グレインフェッドや煮込み料理などから挑戦してみるのがおすすめです。